エンジニアリング組織論への招待
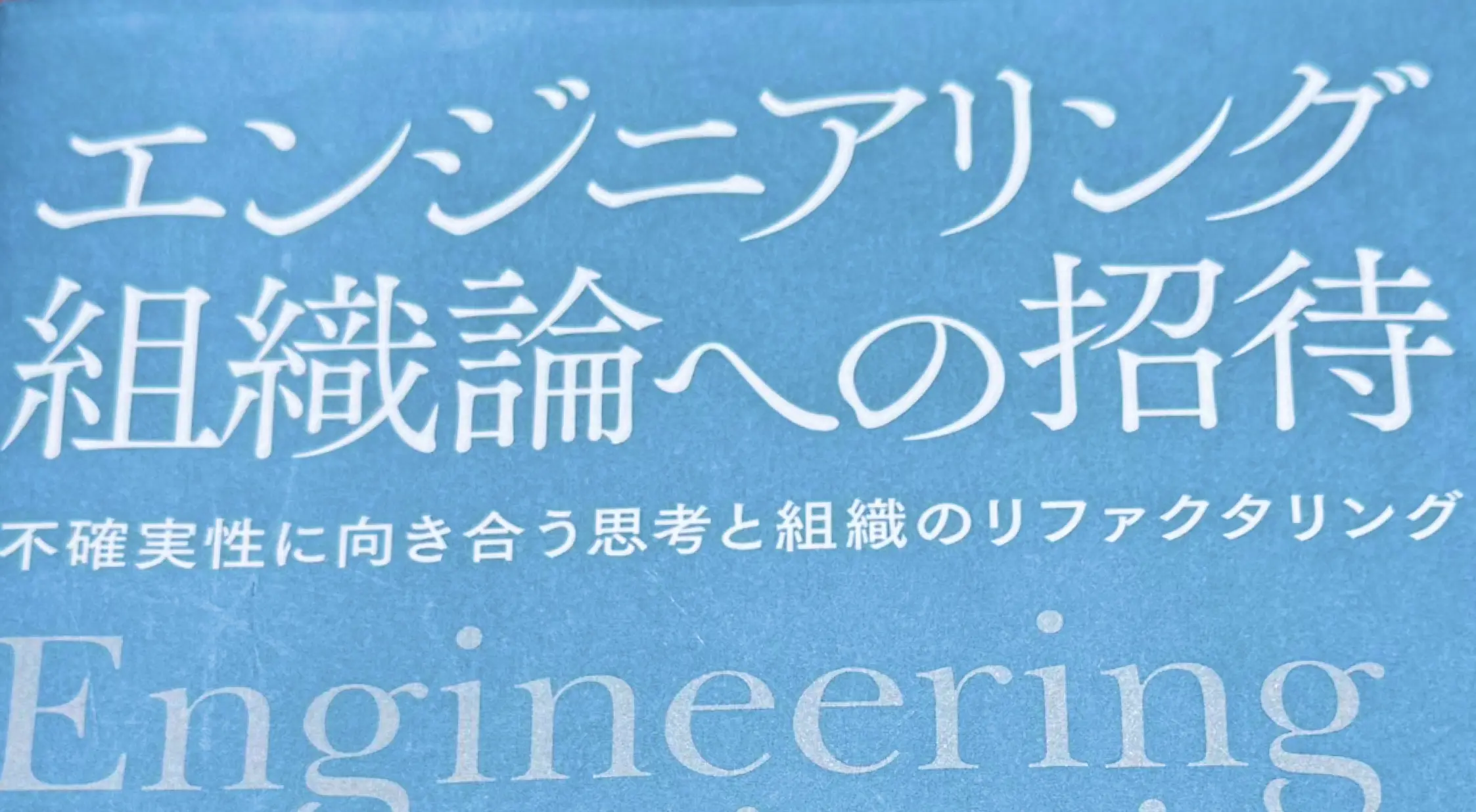
エンジニアリング組織論への招待
1日かけて読んだけど、この本はかなり良かった。
組織に属する人間全員に読んでほしい。
どう良かったのか?
よく飲み会とかリーダーMTGで「部下が⚪︎⚪︎」みたいな愚痴というか悩みを言ってる人がいるが、
前々から「自分の不甲斐なさ」をバラして何がしたいんだろうと思っていた。
そういう人たちのことを本当にダサいと思っていた。
まあ、それを是正できなかった自分はもっと不甲斐ないんですが。
この本は、その気持ちを言語化してくれた。
エンジニアリングとは「実現すること(不確実性を削減すること)」である
今までエンジニアリングの意味について深く考えたことがなかったが、 この本では「エンジニアリング」とは「実現すること」だと定義していた。 確かにしっくりきた。 「誰かの曖昧な要求」を「不確実性を排除して明確に具体的な形」に落とし込み実現していく過程を「エンジニアリング」というらしい。
そして、我々ソフトウェアエンジニアは、 この「不確実性」の解消を「いかに効率よく」行うかを考える必要がある。 この本では、特に技術的なことには触れていない。
不確実性とは「わからないこと」によって生まれる
不確実性とは「わからないこと」によって生まれる。 そのわからないこととは、2つしかない。 それは「他人」と「未来」である。
わからないことを解消するには2つの方法がある
1つは、行動することである。 この本では「経験主義」と言っている。 もう1つは、「仮説思考」と言っている。 「経験主義」は、情報を入手するために行動を起こして、その結果を観察し、そこから問題解決を行う考え方である。 「仮説思考」は、限定された情報であっても、その情報から全体像を設定し、それを確かめることで少ない情報から問題解決に向かう考え方である。
わからないことは調べるしかない
裏向きに並んだ3枚のトランプがある。この3枚のうちハートのエースはどれか? この問題に対して、論理的な思考では解決できない。 1枚ずつめくってみるしかない。
コントロールできないものをコントロールしようとするな
コントロールできないものをコントロールしようとするな。 「他人」をコントロールしようとするな。 「他人」を動かしたいのであれば、まずは「自分」から変わろう。 そして、観察しよう。
PDCAのPはやることを決めることではない
「PDCA」のPは、現在ある情報から、仮説を推論し定め、それを確かめられるような実行計画を立てることである。 仮説ツリーを作ろう。 なるべく確からしい何かを作ろう。
問題解決するために3つの眼を養おう
「視野」:あるポイントから問題を見たときに、同時に把握できる領域の広さ 「視座」:どこから眺めるか。どれくらいの人の立場に立てるか 「視点」:どの角度から見るか
人間の不完全さを受け止める
自分の知性に対する絶え間ない疑いと、自分自身への洞察力。内省する力をつけよう。
謙虚・尊敬・信頼
この3つのうち1つでも欠けたら、チームはうまくいかない。
他者説得じゃない。自己説得。
内発的動機づけという言葉があるが、それに近い。 自己説得を生み出すには、答えを言うのではなく、適切な質問の積み重ねが重要である。
共感と同感は違う
共感:あの人のxxが苦手なんですね。
同感:私もあの人苦手です。
同感する必要はない。
事実の認知は難しい
xxさんがxxって言ってました。
など噂を聞いて、それを事実と認識してしまうことがある。 または、誰かがそのような噂を事実と認識してしまっていることがある。 その場合は、適切な質問をするしかない。
分かった?は意味のない言葉
「分かった?」は意味のない言葉である。 本当にわかっているかを確認するには、それを1人でやってもらうことで確認できる。
目標設定をする意味
・目標設定による主体性向上 ・モチベーションアップ ・問題解決能力の向上
番外編:仕事と学力テストの違い
仕事には答えが存在しない場合がある、また明らかに正解の場合でもコミュニケーションの失敗によって制限されてしまう場合がある。 つまり、論理的に正しいだけでは、仕事では正解(問題解決)に辿り着けない場合がある。